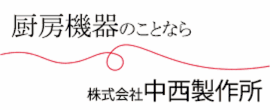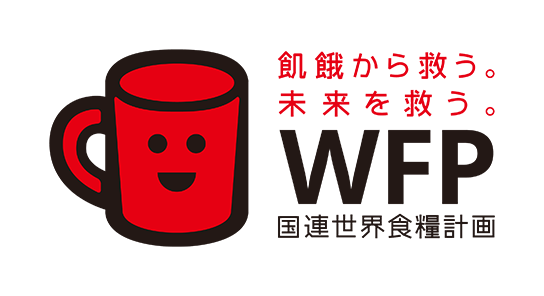芸術の秋です。 そこで、横須賀市の観音崎灯台の近くにある横須賀美術館へ行ってきました。 11月3日まで、食を題材にした絵画を集めた「おいしいアート展-食と美術の出会い」が開催されていたのです。
芸術の秋です。 そこで、横須賀市の観音崎灯台の近くにある横須賀美術館へ行ってきました。 11月3日まで、食を題材にした絵画を集めた「おいしいアート展-食と美術の出会い」が開催されていたのです。
2005年の食育基本法が成立し、日本でも「食育」という言葉や考え方もずいぶん浸透してきました。 西洋ではこの食育にあたるものは存在していたのか、ということを考えたときに、実は西洋美術にその重要なヒントを見る事ができます。 それはキリスト教における「食」の位置づけと言ってもよいでしょう。
西洋ではダ・ヴィンチの「最後の晩餐」のような伝統的な主題を描いた宗教画や、野菜や果物を描いた静物画などにおいて、食にまつわる作品を見ることができます。 最後の晩餐で、キリストはパンを割き、弟子たちに「これは私の体である」と宣言し、ワインの杯をとり「これは私の血である」と宣言します。 パンとワインは西洋の食事の基本であり、この両者に神聖な意味がこめられました。 日々の食事についても、この聖餐の延長であると位置づけられたのでした。 教訓的な食事といえます。 また、万物の創造は神によって成されたことから、様々な食べ物も、神が作り出したものとして考えられ、果物の静物画も、そういった意味がこめられています。
 今回展示されていたセザンヌの「3つのりんご」。 りんごは旧約聖書『創世記』に最初の人間と記されるアダムとエバが天地創造の物語において 「善悪の知識の木」の実(禁断の果実)として食べられる果物であります。
今回展示されていたセザンヌの「3つのりんご」。 りんごは旧約聖書『創世記』に最初の人間と記されるアダムとエバが天地創造の物語において 「善悪の知識の木」の実(禁断の果実)として食べられる果物であります。
セザンヌは「ひとつのりんごでパリを驚かせたい」と言いました。 丸みをおびた量感や色彩を描くことを探求したのです。 19世紀以降ではセザンヌによって静物画が絵画表現の実験場となると、食の表現はますます多様化していきました。 この作品は1877年頃の作品。
 一方、日本では不思議なことに食を扱った絵画は、西洋画に接するまで殆ど見られません。 むしろ、食べ物そのものや、食器や酒器への装飾を以って芸術性を高めていきました。
一方、日本では不思議なことに食を扱った絵画は、西洋画に接するまで殆ど見られません。 むしろ、食べ物そのものや、食器や酒器への装飾を以って芸術性を高めていきました。
今回展示されていた、高橋由一の「豆腐」です。 セザンヌの「3つのりんご」とほぼ同じ時期に描かれた作品です。 本格的な油絵技法を習得し江戸後末期から明治中頃まで活躍した、日本で最初の「洋画家」といわれている高橋由一。
食べ物を描いていますが、日本の場合はすべてのもの中に霊魂、もしくは霊が宿っているというアニミズムの考え方がベースになっています。 そして由一は油絵に馴染みのない人々のために、日常のありふれた生活用品・道具を描いて油絵の普及を図り、特に静止画は、由一によって画題として日本にも定着してきました。
 今回の「おいしいアート展」は、日常の「おいしい」体験であるとともに、食の「生きること=食べること」という原点に戻りつつ美術作品に表された人間と食との関わりを見つめ直すという展示でした。
今回の「おいしいアート展」は、日常の「おいしい」体験であるとともに、食の「生きること=食べること」という原点に戻りつつ美術作品に表された人間と食との関わりを見つめ直すという展示でした。
展示会の構成はI章「食事の前に(農耕・狩猟・採集)」、II章「食材の姿、色、かたち 静物画から多彩な表現へ」、III章「食卓の情景 神々の物語から現代社会へ」、IV章「現代アート×食 楽しく、おいしく!」の4部構成。 食べ物の成り立ちや食べ物の姿、食卓の情景と順を追い、最後に食と美術の未来に期待するという流れです。
右の作品は太田喜二郎の「田植」、1916年の作品です。 紺絣の着物に赤い帯とたすき、 白い手ぬぐい、菅笠を身につけた早乙女がハレの日である田植えをしています。 腰を屈んでの田植え作業で、ほっと立ち腰を伸ばしています。 ベルギーのクラウス直伝の温雅な点描画法を用いて、穏やかな日差しを描いています。 特に日光が降り注ぐ水田の表情が秀逸でした。
今回のおいしいアート展では、近代から現代を中心に、食と美術の関係を120点近い作品が展示されていました。
日本で人気のミレーの作品もありました。 ピサロもシャガールも岸田劉生も藤田嗣治も草間彌生もありました。 みんなが知っているアーティストばかりです。 そしてそれぞれが食にかかわる作品です。 どれも原始的な欲求である「食べる」という普遍的なものが、時代や環境によってどう表現されてきたか、という点において比較するととて面白く興味深いものでした。 生きていることは食べることであり、食べることによっていろんな気持ちになる、食べることによっていろんなイメージが浮かび、視覚化されていることに気づきます。 こういった展示を見るのもひとつの食育になるということに確信を得る機会となりました。